謎解き京極、狂骨の夢 [京極夏彦]
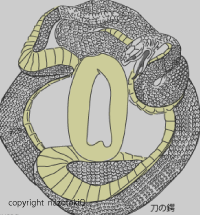
この連作の趣旨、体裁は「謎解き京極、姑獲鳥の夏」で説明した。
あらすじ
1
これは精神的ショックにより記憶喪失となった女の告白をまとめたもの。昭和27年、逗子である。最初の夫、佐田申義は召集に応召せず不審な死をとげた。自分は自殺をはかったところ現夫宇多川崇にたすけられ、ここに定住した。生地は房総の漁村、一松か信州の塩田平、奉公先は信州下之郷の鴨田酒造。恋敵に女がいた。
2
11月1日、早朝である。町田市の釣り堀屋、伊佐間が逗子にきた。海岸で墓参りのように手向けの水をまく女に出あった。持病のマラリアの発症で高熱でくるしむ伊佐間を女は自宅に案内した。切り通しをのぼり二股の道を左にとって家にたどりついた。気づくと仏間で寝ていた。欄間からもれた西陽が反射してた。遠慮する伊佐間をせいして夕食をたべさせてくれた。夫は外出、しばらくかえらないといった。身の上話である。
名前は朱美、生地は信州塩田平の独鈷山のふもと。13歳で奉公にだされ、17歳の時、火事で家族全員が死亡した。雇い主の世話で18歳で結婚、夫は申義といった。召集に応召せず、奉公先の別の女と失踪。その間に病身の義父が死亡。結婚7日めの夜、きびしい取り調べのあとに帰宅すると夫がいた。義父を死なせたとせめられた。事情をきいたがわからない。また失踪。葬式は親切な神主により、すませた。突然、神社の神体は何か。髑髏でないかときく。独鈷山の生家は頭家とよばれ、格式のある家であった。毎年、桐箱から髑髏をだして祀った。女人禁制だった。髑髏を神体とするかよくわからなかった。奉公先で主人にも、民江という娘にもきいた。義父の葬式の話しとなった。
神主にここに髑髏を祀ってないかときかれた、家全部をさがしたがわからなかった。夫はその後、首無し死体となってもどってきた。朱美は厳重な取り調べをうけた。雇い主が民江のことに気づかなかったとあやまり、後始末をしてくれた。町をでた。上田、碓氷峠、本庄とにげて利根川にぶつかった。路銀もつきたので身投げしようとした。そこで民江に出あった。生首がはいるほどの包みをもってた。朱美に気づかずにげようとした。民江とあらそい、利根川に転落した。民江を殺したと思った。伊佐間が朱美が海岸でやっていたことが理解できた。ところで朱美は民江にであった。髑髏はまだもってるかもしれないといった。
3
11月、逗子である。降旗は飯島基督教会で白丘牧師の手伝いをしてる。白丘は新教だが、正教の神秘主義にちかいと降旗は考えてる。白丘は博覧強記である。正教が普遍性をあたえられ、旧教に変遷する。ととのった儀式が形骸化する。それにあきたらず新教にうつる。多数の新教宗派に迷って、自分をきめかねてると降旗は考えてる。
教会にくる前、降旗は精神神経科の医師だった。小石川の歯科医の息子としてそだった。子どものころ、何度もピラミッド状に積むあげられた多数の髑髏をかこみ、多数の男女が交接行為をおこなう、という夢をみた。オンマカキャラヤソワカという呪文も耳にのこった。二人の友だちがこの話しをまともにきいてくれた。青年時代、精神分析のフロイトと出あった。フロイトにはおおくの分派があり互いに批判しあった。ずいぶん学んだ。降旗は学問的に行きづまった。また、自分を分析して醜い姿におののいた。医師を半年でやめ、一年間の放浪後ここにきた。白丘から信者の懺悔をきくという役割をあたえられた。宇多川朱美という女性が懺悔にやっきた。
最初に人をころしたという告白があった。身の上話である。幼くして奉公にだされ、原因不明の出火で家族全員をうしなった。夫は兵役を拒否し失踪した。自分は家をでて、入水自殺をはかったらしい。それを現在の夫にたすけれ、各地を転々として、三年前にここに落ちついた。そのせいで記憶喪失となったらしい。いまも自殺前後はまったくもどらない。不眠症となり夢と現実の記憶があいまいとなった。10月ころ新聞の切りぬきを発見した。それによると先夫は首無しで殺害され、最初は朱美が容疑者、つぎに夫の情婦が犯人と断定されたという。自分と同じ奉公先にいた別人の記憶がよみがえってきた。
別人は、生国、房総一松、両親と兄がいる。性格は卑屈、仕事も遅い。普段から鬱屈をかかえてる。さらに性的に淫らなところがある。自分は山育ち、仕事は要領よく、性格はあかるいという。降旗は理解がむづかしかった。ところが突然、大西、11月、12月にふく強い風がふいた夜、復員服姿で先夫がやってきたといった。
顔の識別がむづかしかったが、誰にもしらせてない佐田朱美という名前をよんだので先夫だという。さんざん非難されたが先夫は去った。現夫が仕事で外出した三日後の夜、またやってきた。さらにその一週間後、現夫が外出した昼間にやってきた。そこであたらしい記憶がよみがえってきた。血だらけの神主が首をもってた。その時、白丘が驚きの声をあげた。また、立派な法体の僧侶の姿も思いだした。髑髏をだいていた。その後すぐに、また先夫がやってきた。無我夢中で首をしめて殺害した。そして首を切断した。降旗は自分が治療するよりないと決意した。先夫はまたきたでしょうときくと、きた、また殺したといった。降旗は先夫がまたきたら殺しなさいと助言した。朱美は辞去した。その後、白丘と論争となった。そのはてに白丘は真の信仰をもてないまま牧師をつづけていると告白した。さらに自分も骨がこわいのだといった。
4
12月、国分寺である。小説家の関口は武蔵野連続バラバラ殺人事件の犯人であり、新進の小説家でもあった久保の葬式にでた。神式であった。喪主はその父、神官は京極堂だった。式が9時前におわり、通夜のようになった。稀譚社の編集員、小泉女史と同じく編集員で京極堂の妹でもある敦子がやってきた。怪奇小説家で関口には大先輩にあたる宇多川崇を紹介し、相談したいことがあると会食にさそった。
中野の軍鶏鍋屋で食事がおわった後、敦子が合流し、宇多川の話しがはじまった。宇多川は57歳、妻は27歳。妻は海鳴りを怖がる。そのうち幻覚がみえるといいだした。宇多川の身の上話である。昭和19年、東京から埼玉県の本庄に引越した。日課の利根川散歩の時、不審な物音で人が流れているのを発見。助けて家で介抱した。まったく記憶をなくしてた。巾着袋から佐田朱美と名前が判明した。記された住所により下之郷にいった。夫は兵役忌避、首無し死体で発見。その後出奔。一月前のことだった。紹介されて鴨田酒造の鴨田周三にあった。その時、甥が出征した。憲兵がまだ朱美の行方をさがしてる。もどらないほうがよいといわれた。そこで事件を報道した新聞切り抜きをもらった。朱美をしる佐久間老人とあい、本庄に同行してもらった。南方朱美だと確認できた。ほとんどの記憶がもどってきた。
昭和21年東京にもどった。そこに元憲兵がやってきた。引越しを繰りかえし逗子に落ちついた。10月新聞切り抜きを妻が発見した。ついに先夫を自分が殺害し、容疑者も自分が殺害したと告白した。しかし宇多川は新聞記事からこれを否定。朱美は先日、先夫がもどってきたといった。これも否定。手形という物証があった。しかし朱美は先夫は繰りかえしやってきた。ついにはそれを殺害した。都合三回も首を切断したといった。家の庭中が血だらけだった。今日は隣りの奥さんにたのんで外出した。親切な隣人は一週間前にもたずねてくれた。二人は探偵の榎木津と、精神科の医師に依頼することを約束した。
おことわり
京極作品を未読の皆さん、どうかここを不用意にのぞいて将来の読書の喜びを損なわないよう、よろしくお願いする。
再度の警告。本文にはいわば「ネタバレ」が溢れている。未読の方には勧められない。では本文である。
謎解き京極、狂骨の夢
1
昭和二十七年、逗子である。海鳴りが嫌いだ。そもそも海が嫌いだ。私は海のないところで育った。海の近くに住むようになって数年になる。眠る。そして夢を見る。真っ白い骨になって海に沈んでゆく。また浮かびあがる。丸い夜空だ。私は井戸の中にいた。いくどもこんな夢を見た。私が生まれたのは房総の一松(ひとつまつ)という小さな漁村だ。何という唄か知らないが着飾った船方たちが唄う唄を覚えている。ここ何ヶ月か私の精神は不安定である。変な夢を見る。私が生まれたのは信州の山村である。長女だった。十三歳のときに造り酒屋に奉公に出た。十七のときに生家が火事になり家族全員が焼け死んだ。造り酒屋の主人が親切に嫁入り先まで世話してくれた。夫となった人は実直そうな農家の青年だった。病気の父親と二人暮らしだった。すぐに召集令状が届いた。
その後である。私の記憶が欠落している。その頃私は一度死にかけた。すべての記憶を失なった。一年以上をかけ徐々に記憶を取り戻してきた。すべてを思い出したと思ったが、夫に召集令状が来たときから、その後のこと、何故記憶を失なうようなことになったのか、この部分が思い出せない。夫は戦争に行くことなく不審な死をとげた。周囲の非難を浴びる中で父は病死し、私はどうやら投身自殺を図ったようだ。そして現在の夫に助けられた。夫は三十歳年上である。内縁関係のまま気がつくと八年が経過していた。私が最初に意識を取り戻した場所は最初の夫の住所ではない。しかしどこかわからない。夫は何度も引越しを繰り返した。この海鳴りのきこえる家に来たのは三年前だった。夫が何をしている人なのかわからなかった。しかしやがて宇多川崇という怪奇小説家であることを知った。昨晩夫は戻らなかった。私は起きて、遅い朝食を済ませた。何もすることがないので箒を持ち出し、すこし掃いた。眩暈がした。
私は売られていった。下働きだった。ずいぶん心細かった。懸命に働いた。額に黒子があったとか、目尻の皺が深かったとかをはっきりと覚えているが、どんな顔だったのか思い出せない。私はそのような性質だったらしい。よく人間違いをして叱られたり笑われたりした。馬鹿だといわれたときは悔しくて、故郷のあの海の音を思い出した。私は障子にもたれるようにしてしばらく気を失っていた。白昼夢を見たようだ。私が住んでいたのは塩田平で奉公先は下乃郷の鴨田酒造だった。海の風景、一松という地名は白昼夢だ。どうしてこんなに鮮明に浮かで来るのか。書斎に入って地図を見た。一松という地名があった。これは偶然なのか。また海鳴りだ。
売られて三年たって、ようやく親切にしてくれる友だちができた。同じくらいの年格好、下働きの娘だった。その名前が思い出せない。名前が浮かんできたと思うと眼が覚めた。地図帳に突っ伏して居眠りをしていた。もう西陽の入る夕方となっていた。立ち上がってよろめいたときに棚から資料が落ちた。また海鳴りがきこえる。私は何故あの方があの女を選んだのか、怨んでいる。涙を流している。その女の名前が出そうで出てこない。手に掴んだ資料を見る。「兵役忌避者、首無し遺体で発見」、「新妻の犯行か」、「情婦を指名手配」とある。頭が混乱する。あの人の首を切り落すなどはできない。それはあの神主のしたことだ。私はただあの女だけを怨んでいる。資料を握ったまま寝所に向う。兵役忌避者、佐田申義の名前が浮かんできた。それは私の最初の夫の名前だった。私が疑われて厳しい追求をうけた。夫は今日も帰らない。あの女の名前が出てこない。金色の髑髏が浮かでくる。そのまま意識が遠のいた。
2
十一月一日、逗子である。町田で釣り堀屋を営む伊佐間一成は十月、山陰を約ひと月間、釣旅行した。町田で二週間を過ごし、湘南で釣では未踏の逗子にやって来た。十月三十一日に鎌倉に入り、木賃宿で一泊した。早朝三時出発し名越の切り通しを越えて五時に逗子に入った。六時、釣果がないので場所を変えようとした。海岸を女が裸足で歩いてきた。右手に手桶と脱いだ下駄、中に菊の花、左手に柄杓を持っていた。まるで墓参のようだった。女が伊佐間を見て笑った。伊佐間がこんな寒い時期に墓参りかとたずねた。女は伊佐間の方が寒いだろうという。伊佐間はマラリヤ罹患の後遺症で熱に弱い。今朝の強行軍で風邪を引いたようだ。どこか近くに休めるところはないかときく。女はそれに答えず、燐寸を所望した。もらった燐寸を何本も無駄にして線香に火をつけた。それと菊の花を海に投じ、柄杓で水をかけた。これは清水だといった。けげんそうな顔に気がついた女が亡夫の月忌日だという。そして伊佐間を自宅に誘った。伊佐間は発熱でくらくらしていた。
女の家は切り通しの坂を登った先にあった。二股に道が分岐したところで声をかけられた伊佐間は左に進んだ。切り通しの奥に両側の壁に挟まれるように古い日本家屋が建っていた。通された座敷には火鉢が置かていたが寒かった。本格的に風邪の症状が出た。女は台所から卵酒を持って戻ってきた。伊佐間の様子を心配して横になるように勧めた。伊佐間は熱々の酒を呑むにつれて眠気が襲ってきた。気がつくと仏間に敷かれた布団の中だった。遠慮するのと勧めるののやりとりがあったような記憶があった。仏壇が置かれていて、欄間から差込む西陽が反射していた。女が部屋に浴衣の着替えを持ってきた。そして丹前を羽織って出されたお粥を食べた。女は朱美と名乗った。夫がいるが、しばらく家を空けて今日は戻らないという。女は伊佐間の人柄を見込んで安心しているようだ。物騒なご時世であるので泊ってくれという。私は人を殺したという。意外な発言に驚くとともに興味が惹かれて泊ることとした。自分のためといって酒の支度を整えて、酒肴代りといって身の上話をする。
朱美は信州の塩田平の生れだという。実際に生れたのは独姑山という山の集落だが、もの心ついたころ塩田平に移った。十三のとき奉公に出された。三年もすると里帰りが許された。十七のとき、ちょうど里帰りの翌日に実家が火事になり、家族全員が亡くなった。親切な雇い主の計らいで奉公先から嫁に出してもらった。十八のときだった。これで幸せになれると思ったが、すぐに夫、申義に召集令状が届いた。さらに父親が癩病だった。話しがつづく。申義は実直そうだったが実は同じ奉公先の娘とできていたらしい。申義はその娘とともに逃げた。壮行会まで済ませて逃げたという。七日めの夜、厳しい取り調べの後、朱美が家に帰ると申義がいた。申義に文句をいおうとすると逆に義父をほったらかしにしたと詰られた。申義は薬を飲ませに帰ってきたという。事情を話したらすまないと謝った。どうして逃げたのかきいたが、しようがなかったというばかりで、まったく要領を得なかった。義父を頼むといったまた家を出た。話しがつづく。
義父は五日もしないうちに死んだ。葬式も出せなかった。これは親切な神主がいて、こっそりとお祈りをしてくれた。突然、朱美が神社にお祀りしてあるご神体とは何かとたずねた。とまどう伊佐間にあれは髑髏ではないかという。朱美が生家のことを話す。昔、独姑山中にいたころ、頭家と呼ばれていた。朱美の実家は遥か昔は格式のある家柄だったという。その証しとして絹で包まれ桐箱に入った家宝があった。年に何度か灯明が上げられ、お神酒が備えられ、祝詞が唱えられた。女人禁制の家宝であった。これを持っていることが頭家と呼ばれる由縁であることに気がついた。奉公に出る前に中を見た。それは髑髏だった。ずいぶん大きなものだったという。それで何故そんなものを祀っているのか不思議に思ったので、つい奉公先できいてみた。結局、わからなかった。奉公先の主人、下働きの民江という娘にもきいたという。火事の話しとなった。朱美が髑髏も焼けてなくなったというが、伊佐間が骨は残るだろうといった。結論は出なかった。義父の葬式の話しに戻る。
神主が義父に世話になったといってお祈りをしてくれて、ここに何かお祀している箱がないかとたずねた。どうやらその中には髑髏が入っているらしいという。伊佐間は髑髏崇拝が秘密裏に行なわれていたのではないかと思った。朱美は神主といっしょに家の中を探したがなかったという。ここで朱美が立ち上がり浅蜊鍋を持って戻ってきた。伊佐間は話しの先を促した。申義は義父の死後、三日めに首無し死体で戻ってきたという。首は死後切断された。その行方は不明のままである。内股に特徴のある疵があるので本人に間違いない。何故首を切られたのかわからないという。犯人は民江だったという。
朱美も一時容疑者となった。憲兵隊に勾引され厳重な取り調べをうけた。そのときに申義は殺害されたことが判明し、不在証明となった。民江は申義と同じころに失踪した。朱美は結婚当時の民江の様子が変だった。精神的には未熟だったが、肉体的には成熟していた。同室だったが夜にこっそりと部屋を抜けだすのを目撃したという。ふたつの失踪を結びつけて考えたのは主人だった。主人は民江が指名手配となったときに朱美にこっそりと謝りにきたという。義父の埋葬に困って自分で庭に仮埋葬した。主人が気の毒がって後始末を引き受け、町を出るようにいって金を包んでくれた。すぐ出立した。上田に出て碓氷峠を越え、本庄までやって来た。そこで路銀も尽きた。利根川に身を投げようとした。そこであの民江と邂逅した。民江は顔を隠すでもなく無防備に川縁をひとりとぼとぼと歩いていた。その時丁度生首が入るほどの包みを持っていた。あれは申義の首だと直感した朱美は民江の正面に立ちはだかった。民江は朱美の顔がわからなかった。事件後、ひと月経っていた。どなたですか。先を急ぐ。これから逗子に行くといった。朱美はその首を返せといった。ふたりは爭った。朱美は無我夢中で民江の首を絞めた。そして水中に顛落した。私は民江を殺したといった。その後の話しがつづく。
朱美は親切な人に助けられて一命を取り留めた。民江に悪いことをしたと後悔した。首の行方について朱美は必死で民江の首を絞めていたからわからないという。伊佐間は海まで流れていった。今朝の朱美の供養はそのためだと理解した。骨が焼けても残るという話しに戻る。骨となった申義の首にどのような思いが残るのかという。朱美は伊佐間にもたれかかる。驚く伊佐間に民江がいたという。民江はまだ申義の髑髏を持っているかもしれないといった。
3
十一月、逗子である。降旗弘は飯島基督教会で牧師の手伝いをしている。そこは白丘亮一という牧師がいる新教の教会である。
白丘は基督教史について博覧強記である。事実、降旗は白丘により新教と旧教の違いなど基督教につい多くのことを学んだ。しかし自己の信仰については語りたがらない。降旗は白丘の信仰の中核には神秘主義であると睨んでいる。それは正教に近い。だから白丘の信仰の出発点は地域・民族主義的で、神秘主義的である。正教をより普遍的なものにしようとして、結果、旧教ができ上がったように、模索の中にひとつの様式を得た。しかし様式が完成すると形骸化する。これを排除しようとして新教が誕生した。白丘の中でも新しい様式が生まれたが、そこに留まれなかった。さらに純粋な信仰を求めて新教が多数の教派を生んだように、多数の様式が生まれた。その結果、白丘は多くの葛藤を抱えこんだと理解している。話しはつづく。
昭和十六年、日本の新教教団は「日本基督教会」の名のもとに統合され、当時の国策である軍国主義を神学用語で擁護した文書を作成したという。戦争が終ったが、教会は何もしなかった。白丘の葛藤は今もなおつづている。降旗は一見、ひょうひょうとしているがこのように迷いつづけている白丘が気に入っている。降旗はしかし、恩人であり友人である白丘をこのように理解する自分、どうしても分析してしまう自分に嫌気がさしている。身の上話となる。
教会に来る前は精神神経科の医師だった。その仕事は半年しか持たなかった。降旗は小石川の歯科医の息子として育った。子どものころ軍隊遊びが嫌いだった。勝ち負けを争っても最後は死ぬ。死ねば骨となり同じだと思った。父から弱虫と誹られたが、口答えはしなかったが、やはり同じで、最後は骨になると思った。母は基督教信者だった。優しかったがそれ以上に頼りになる存在ではなかった。やはり骨となれば同じと思った。幼い頃から同じような夢を見る。夜の闇の中に炎が立ち上がっている。その周囲に男女の組が座っている。オンマカキャラヤソワカという呪文が何度も唱えられる。全裸の男女が交接行為をしている。中央に積みあげられているのは髑髏であった。大量の髑髏がピラミッド状に積みあげられている。どうしてこのような夢を見るのかわからない。我慢できなくて、友人にその夢を語った。まともにきいてくれなかった友だちの中に、シュウさんとレイジロウという二人がいた。シュウさんは、変な奴だ。二百三高地の夢でも見たんだ。レイジロウは、面白い。僕も見たい。君は狡いといった。この奇妙な夢をまともにきいてくれて、それぞれの感想を述べる。それだけで十分だった。今だったらそう思う。しかしその時は満足できないで、その先を知りたいと思った。青年時代の話しがつづく。
すこし変っている大人しい男という周囲の評価で成長した。いつもぼんやりとした不安があった。その不安を取り除きたいと思った。最初は哲学を齧った。それから宗教を撫でた。不安は消えなかった。そして精神分析のフロイトと出会った。高等学校時代は無性に魅かれた。当時、フロイトは文学として受け取られた節があった。複数の解釈があり得る文学は嫌だった。降旗が安心するためにはそれは科学である必要があった。医学としての精神分析を学びたいと思った。しかし当時のフロイトの精神分析は治療するための医学としては認知されていなかった。分析をする学問だった。国内で学ぶのは困難だった。結局、精神分析に理解のある教授のいる医学部を備えた大学に進んだ。大学の外で精神分析を学んだ。紆余曲折の末、日本で珍らしい精神分析を学んだ精神神経科の医師となった。精神分析学の話しがつづく。
フロイトの精神分析学は創始されて、たかだか五十年、まだ真理に到達していない若い学問である。多くの分派が存在し互いに批判し合っている。降旗はそこで懸命に学んだ。そして、精神分析学は、人間を理解する方法であり、神経症を治療する方法であり、その二つの集積により得られる学問自体でもあるという結論に達した。治療のため精神分析を進める。それにより人間理解が進み、新しい理論が生まれる。その理論により、新しい方法による分析を進める。さらに新しい理論が生まれる。このあたりで降旗は学問的に行き詰まった。さらに、自分自身の分析により得た自身の醜い姿を直視することができなかった。フロイトを否定してみた。また違う姿に出会った。それにも耐えられなかった。いつもフロイトに戻った。ある時フロイトの先を見たような気がした。たしかにした。そしてフロイトは呪いのようなものだと気がついた。やる気がなくなった。その時既に医師として働いていた。そこで自分の不適格を認め辞職した。一年間の放浪の後にこの教会に来て、半年になる。白丘から信者の懺悔をきくという役割を与えられた。話しがつづく。
新教において旧教のような懺悔はない。ただ、話しをきいて、最後に悔い改めなさいといえばよいという。月に一人くらいの頻度で懺悔をきいた。そこで降旗は自分は人のいうことをただそのまま受け止めることができず分析してしまう。その分析してしまう自分が嫌だったのだと気がついた。フロイトの所為にするのは逆恨みであった。白丘が懺悔をしたい信者がいるという。降旗の方が向いているという。和服の女性は宇多川朱美と名乗った。
私は人を殺したと告白がはじまった。死人が戻ってくるともいう。身の上話がはじまった。貧しさ故に幼くして奉公に出され、原因不明の出火により家族全員を失い、結婚した途端に夫に召集令状が屆く。夫は重病の父を残したまま兵役を拒み出奔する。幸福とはいえない半生である。自分は周囲からひどい仕打ちを受けた。義父が死に、家を出た。そして入水自殺を図った。その所為ですべての記憶を失ったという。今話したことも時間をかけて思い出したものである。しかし自殺を図った前後はずっと戻らぬまま過してきた。自分は現在の夫に救出された。それからは何事もなく過ごした。元いた村には戻らず、各地を転々として三年前にここに落ち着いた。ここに引越してから自分はすこしおかしくなったという。朱美は海鳴りが嫌いだという。話しがつづく。
だんだん眠れなくなった。無理に眠っると夢を見る。骨になる夢だった。何度も見る。それは自分が自殺した時の記憶でないかという。降旗がどうしてそう思うようになったのかときく。十月ころ新聞記事の切抜きを発見した。それによれば、出奔した夫は殺害された。その遺体は首が切断されていた。最初は朱美が容疑者となり、その後、別の娘、夫の情婦が犯人と断定されたという。その記事を読むにつれて、記憶が断片的に甦ってくる。例えば、首のない夫の死体の有様などである。そこで自分の見る夢はあの世の光景ではないかと思ようになったという。さらに記憶には他人のものが混じるようになったという。
生国は上総の一松、両親と歳の離れた兄がいる。十歳になる前に売られる。その先は信州の塩田平の造り酒屋である。その時代は不明である。そこで苛められる要領の悪い娘である。朱美が奉公していた同じ造り酒屋だったという。それは夢で見るのかときく。夢かもしれないが区別がつかないという。降旗がもうひとつの人生も本当の人生も同じように見えるがというと、自分は山育ちで海は知らない。奉公に出たのは十三歳、弟や妹がいたが兄はいなかった。あきらかに違っていると思うという。一松という地名はたしかに上総に存在したのかときく。存在したという。売られたというが時代は現代かとたずねる。髷を結ったりしてない。顔触れに見覚えがあるかとたずねる。それは覚えているが比較できないという奇妙な返答であった。話しがつづく。
不思議なことに、海育ちの方の世界の自分と朱美の世界の自分とでは、はっきりと性格が異なっている。海育ちの方は、卑屈であり、仕事もうまくできない、愚鈍を責められても言い返せないでいる。ところが朱美の方は仕事は人並以上であり、鬱憤が溜るようなこともなく、うまくやっているという。海育ちの方は何かを非常に怨んでいる。暗澹たる気分になるという。さらにこの場所にふさわしくないがと断わって次々と淫らな記憶が蘇えってくる。誰とも知れぬ男と痴態を繰り広げているという。朱美自身にはそのような経験はまったくないという。朱美はさらにいう。それは夢というより、起きているとき突然自分の記憶の中に出現するという。降旗が自分の知識を動員して朱美の言葉を理解しようとするが、それでは理解できないもののようである。それを整理して、朱美は常に朱美という人格を保っていながら、朱美と全然違った考え方や行動をとる過去の朱美を思い出すということかという。降旗は困惑する。白丘も困惑する。再び降旗がたずねる。
朱美の主人に相談したか。一月前にした。主人は溺れた朱美を助けてくれ、記憶を取り戻す手助けをしてくれた。しかし前の夫の不幸な事情は黙っていたという。先月から耐えがたいほどおかしくなったと感じたので相談したという。夫はそれは前世の記憶ではないかといったという。迷信かもしれないが、それでも気持がすこし楽になった。ところが、大西、十一月、十二月に吹く風のことだが、それが吹く夜、亡くなった前の夫がやって来たという。復員服を着た男は、漸く会えたなという。どちらさまですかときくと、自分で呼んだのに惚けるなという。宇多川が呼んだのかというと、お前、佐田朱美が呼んだという。佐田朱美という名前は誰にも知らせていないので、朱美は冷水をかけられたようにぞっとしたという。降旗がそれは本当に前の夫の顔だったかときく。顔の識別は難しかったが別の誰かがやって来るとは思えなかったからという。降旗の疑念を残し、話しがつづく。
申義は朱美を睨んで、朱美が知らせたから来たといった。朱美は覚えがないという。申義はよくも八年ものうのうと暮らしていたな。亭主を殺しておいてといった。降旗の問いに、新聞では犯人は宗像民江である。だが自分が犯人でないという自信がもてない。資料によれば自分には不在証明がある。しかし、たぶん自分が犯人だという。降旗は潜在思考の願望という言葉を思い浮かべた。たぶん、自分が犯人という考えをはっきりさせるために、無意識にこの男を出現させたのだと思った。それが朱美の病根だと理解した。さらに男がいう。お前の旧悪を暴くためにあの地獄から生還したという。ここで朱美は申義の首を絞めている情景を思い出した。殺害行為の断片を思い出したという。民江も自分が殺したのだろうという。降旗は朱美の話しを分析しその結果に納得した。話しがつづく。
申義は、朱美をどうするか決めかねている。また来るといって去ったという。夫は心配してくれたが、三日目仕事の都合で外出した。その夜、また来たと。復員服を着た男は見つけたぞといった。朱美はその場にへたりこんだ。男はそこで朱美を犯した。朱美はいいにくそうに、申義だといった。その後、申義は髑髏を出せといった。知らないという朱美に、それは俺のものだといった。朱美は翌朝までずっと失神していたという。夫からは医者に行けといわれたが、自分のいっていることは到底信じてもらえないと思って行かなかったという。夫はずっとつき添って、犯人は民江であること、現在、失踪中であることを説明してくれ安心した。しかし鮮明に蘇える記憶の断片はどうすることもできなかったという。降旗は夫の説明により朱美の願望はいったん抑えられたと解釈した。一週間経ってまた夫が外出したという。
今度は昼間に復員服の男が訪れた。戸を開けずただ帰ってくれといった。戸を敲く音はやがて止んだ。朱美はまた新しい記憶が蘇えってきた。たしかに首のようなものを持っていた。自分が切ったものではない。血だらけの神主が首を持って立っていた。朱美は物陰からそれを見ているという。白丘が血だらけの神主かと声をあげた。降旗は神主は朱美が認めたくない新し欲動だろうと解釈した。その神主の顔に見覚えがあるかといきく。答えられない。顔は識別できないという。思い出したのはそれだけかときく。記憶の中の朱美はその神主を見て、ああ、お坊さんのところに行かねばと考えている。そのお坊さんは、紫色の法衣、袈裟、帽子を被った立派な方だった。そのお坊さんが髑髏を抱いていたという。降旗は懸命にその意味を考える。その神主とお坊さんの関係をたずねたが、ただ怖いと思っただけという。すると間を空けずまた復員服の男は訪れたという。降旗はこれで意味がはきりすると思った。
朱美は主人が恋しくてたまらなくなったので思わず戸を開けた。復員服の男が立っていた。髑髏はどこか、井戸の中かといって入ってきた。何が何だかわからなくなって、その背中にすがりついてもがいているうちに、気がつくとまた申義の首を絞めて殺していた。また生き返っては困るのでその首を切断したという。降旗は何重にも隠蔽したいという朱美の気持が理解できた気がした。やっと安心した。さてどう治療したものかと考えた。白丘が止めるのを無視して、どうやって切ったのか。どんな気持だったかときいた。そして白丘には詳細にきかなければ正確な分析はできないと答えた。鉈と鋸を使った。それは納屋にあった。普段使っている包丁を使おうとは思わなかったのか。それでは料理が食べられなくなる。どうやって切ったのか。死体を中庭に運んで庭石の上で切った。首は裏に廻って海に放った。身体は井戸に落した。それはとうに涸れていた古井戸だった。それからどうしたのか。風呂に入った。すると落ち着いたが、海鳴りがしてきた。着替えて寝床に入り寢た。しばらく考えていた降旗がさらにきく。
死人は首を切っても死なないでしょう。先夫はまた来たのでしょう。白丘がまた止めたが、朱美が申義はまた来たという。白丘が絶句する。また殺した。また首を切ったのか。鉈と鋸で切った。白丘が止めた。常軌を逸しているが必要だと降旗。さらに詰問するように、個人的にききたくない理由があるのかと反発した。降旗と朱美の問答である。何故この教会堂に来たのか。基督教徒でも仏教徒でもない。あの世も来世も信じていない。でもそんなものを持ち出さないとこの不可解な現象の説明がつかない気がしたから。それでも、それより何かの病気だという解釈で筋が通ったほうがよいのか。然り。では病院でも神社でもお寺でも警察でもよかったのに、何故教会に来たのか。警察は殺人者だから。罪の確定か。病院は牢屋のようなところに留置される。異常性の確認か。お祓いが必要だとすると、神社だが、そこに行くのは怖かった。生首を持った神主か。お寺に行くのも抵抗があった。髑髏を抱えた僧侶か。それで教会に来たと降旗が理解する。降旗は朱美の答えに次々と解釈を見つけていた。朱美が、引越したばかりの頃、この前を通った。その時主人が基督教は悩める者を救うところといったのを覚えていた。もう限界だ。助けてくれという。白丘が安心させえるように先夫はもう最後の審判の日まで蘇えらないというと、降旗は朱美がすべてをきちんと認識するまで先夫は何度でも蘇える。朱美は何度もその首を切るという。降旗は朱美は自分が治療するよりないという。降旗が朱美に語りかける。
先夫はまた訪れるでしょう。来たら殺しなさい。先夫は陵辱しても傷つけることはできない。ただ絶対に首を切ってはいけない。その死体の横で何故首を切り落とさなければならないのかを考えなさいという。生き返るのが怖かったからといったが、それでも生き返ったから、朱美が首を切るのには必ず別の理由がある。それが見つかればもう来ないといった。朱美はしばらくじっとしていたが、やがて立ち上がり、礼をいって立ち去った。降旗が白丘に暴言を詫びた。朱美が真実の姿に思い至った時、そこからは白丘の出番だといった。白丘は朱美のいうことのすべてが妄想とはいえない。いくらかは実際に起きたことだと思うという。降旗が朱美のいったことはあり得ないことだ。輪廻転生、死者の復活を信じているのかと問うと、ないという。ふたりの間に論争がはじまる。
白丘が朱美の話しのうち、死者が甦ったというところは想像の産物とは思えないというと、そうは思わないという。そこにはずいぶんと現実感があるというと、それは認めるが、それが現実とする合理的説明ができないという。強盗が入ったとするとどうかというが、そんな強盗はいないという。先夫が本当に訪れたとしたらどうかというと、その死亡を警察が確認している。間違いがあるとは思えないという。仮に警察が間違えたとして、朱美が別人を殺害した。あるいは夫が犯人だった。共犯だった。こんなことは納得できない。記憶喪失の件がある。回復した後でないとこの話しは成立しない。都合がよすぎる。さらに降旗が反論する。強盗にせよ先夫にせよ、複数回殺害が繰り返された。あり得ない。降旗が朱美は先夫を殺害し首を切断した。それを長く抑圧隠蔽してきた。それをどうしても認めたくなかった。朱美の心の中核に死を好み破壊を好む殺人淫楽症的素養があったといった。それはあんまりな表現だという白丘にたいし降旗は現実にそんな人が存在する。それを直視してないだけだといい、ついに白丘が真実を直視できないから本当の信仰を持てないのだといってしまった。降旗は自分にそんなことをいう資格がないことを自覚しながらそういったことをひどく後悔した。白丘が告白する。
自分はいまだ真の信仰を持つことができない。いつかなんとかなるだろうと牧師をつづけているいいかげんな男だと怒りもせずにいう。そんなことより朱美は大丈夫か、降旗のいうとおりなら、三度、先夫を殺し、今度、また殺すこととなる。苦悩の表情の降旗に君も大変だといって、実は降旗と同じように自分も骨が怖いのだ。それに朱美がいっていた血だらけの神主といったが、降旗はその末尾がきこえなかった。
4
十二月、国分寺である。小説家の関口巽はバラバラ殺人事件の犯人である久保竣公の葬式に出席した。神式で行なわれる葬式ははじめてであった。神官は京極堂であった。京極堂は中野にある神社の神主であり、古書店を営み、副業に憑き物おとしのお祓いをしている。久保は新進の作家として登場し、受賞により注目を集めたが、事件により凶悪犯として世を去った。この事件に関口も京極堂も深く係わった。十一月末、久保の父親が京極堂を訪れて葬儀の執行を頼んで本日に至った。葬主、小数の参加者を前に京極堂が式の言葉を唱える。
式のまにまに箱厚く固く造りもうけて
今し静けく安けく収めたてまつる久保竣公の命の霊魂の御前につつしみ敬いまおさく
あはれ口惜しきかも
あえなくこの現世を神去りまして
百足らず八十の隈道の遥けき幽世に雲隠りたまいぬ
かれ親族家等をはじめ内外の人々に至るまで
集いはべりて天翔りましし霊魂の
安けく鎮らんことを祈ぎたてまつりて
終夜いましし世の御功績をたたえまつり
ゆかしき面影を慕いたてまつるさまを
御心も平穏にきこしめせと
つつしみ敬いまおす
京極堂がいう。葬式はもっぱら寺の仕事であった。氏子の葬式を神社が行なうこととなったのは昭和に入ってからである。久保は修験道や伊勢神道に詳しかったが神道の信者ではなかった。もちろん仏教徒でもなかった。葬主が京極堂を訪れて故人は大罪を犯したがその罪の半分の責めは自分が負うべきもの、何とか供養してやりたいという。もっともである。神道の神は仏教や基督教の神と違う。激しい怨みを持った怨霊も神として祀ることができる。そこで故人の葬儀を引きうけることとした。それと同時に出家を予定していた葬主に神主となり故人を末永く祀るようお願いし了解してもらった。この後、葬主は故人に縁のある九州に渡るときいている。故人の荒魂が和魂に変るべく祀るようお願いする。また言葉を唱える。
いやはての御別れとたてまつる玉串の榊葉の白玉に
こころも取添えて手向けたてまつるさまを
御心平穏にうけたまえと、つつしみ敬いまおす
葬主は丁寧に礼を述べ神主に導かれて退出した。残った者は部屋を移して通夜のようになった。関口は事件に係わった刑事の青木とともに部屋の隅にいた。黙りがちであった。そこに関口が小説を寄稿している稀譚社の担当の小泉女史と京極堂の妹であり同じく同社の編集者の敦子がやってきた。小泉が作家で同じ分野で大先輩にあたる宇多川崇を紹介した。宇多川は挨拶を終えると相談したいことがあるという。会は九時前にお開きとなった。中野の軍鶏鍋屋に案内された。宇多川はよく食いよく喋った。鍋があらかただしだけになった頃、敦子がやってきた。やっと本題に入った。
小泉は二年ほどの付き合いであるが人物を信用している。男性には相談しにくいことがあったので小泉に相談したところ関口と敦子を紹介してくれたという。関口は精神科の心の病気に詳しい。敦子は不思議な話しに詳しいときいた。話しをきかせてほしいという。実は妻の様子がおかしい。宇多川は五十七歳、妻は二十七歳である。山育ちの所為か、海の音を嫌がっていた。そのうち怖がるようになり、幻覚が見えるという。幻覚というのは自分が以前、前世の記憶を持った女の話しを小説に書いた。そんなことかもしれないという。井中の白骨という小説について語る。
主人公の女性は幼くしていろいろな風景や体験の記憶を持っている。さらに長ずるに連れ家屋の様子や地名、人名まで語りだす。そしてしきりにそこに行きたがる。それならばと祖母に連れられゆくと、何もかも記憶どおりである。その家のひとり娘は丁度主人公の生まれた時分に神隠しになっていたことが判明する。これは娘の生まれ変わりだということになる。後半の話しである。主人公はひとり娘が神隠しに会ったのと同じ歳に恋をし、両方の親に祝福されて結婚する。しかし初夜の晩に主人公は夫を惨殺する。死体の側に座っていた新婦はひと言、井中を見よという。井戸を浚うと白骨が出てきた。それは神隠しに会った娘の亡骸だった。前世の怨みを現世で晴らしたというものである。ここにあるように現世で自分が経験したと思えない記憶が蘇えってくるという。敦子がはじめて見たのに、前に見たことがあると感じることはあることである。気分を変える意味でも引越しを検討されたらというと、それに踏み切れない事情があると、宇多川が身の上話をはじめる。
宇多川の妻は朱美という。二度目である。大正の終りに結婚した最初の妻は二年ほどで病死した。宇多川はその後の十八年間は独身であった。戦争が激しくなった昭和十九年に東京から埼玉県本庄に引越した。宇多川の日課は散歩と読書であった。江戸時代の黄表紙や合本、洒落本、浄瑠璃集などをむさぼり読んだ。本庄には神無川、利根川が流れている。その川縁を散歩しながら物語を紡いだという。秋が過ぎた夕方、利根川の川縁を散歩していた。と、何やら人が争う声がした。水辺に下りてうかがうと真ん中に人らしきものが流れてゆく。無我夢中で岸辺に引き上げた。それから自分の家に連て帰り介抱した。それが現在の妻であるという。ようやく息を吹き返した女は記憶を失っていた。まったくなかったのかと敦子がきく。
なかった。しかし手に持っていた巾着袋から身元が判明した。そこに佐田朱美と書いてあった。長野県上田下乃郷とあった住所を訪問した。素性はすぐわかった。夫が兵役忌避者で、首無し死体で発見された。ひと月ほど前に出奔したという。地元の人から鴨田酒造の主人、鴨田周三を紹介された。訪れると丁度その主人の甥が出征するところだった。場違いな感じがしたが主人に話しをきいた。親切に朱美のこと教えてくれた。朱美を救ったことを感謝した。そしてここに戻ることは止した方がよい。夫殺しの嫌疑は晴れたのだが取り調べをした憲兵がその行方を捜しているという。新聞切抜きをもらい、鴨田酒造での様子も教えてもらった。しかし断定するにはまだ不安を感じた宇多川は朱美をよく知る旧知の人、佐久間老人を紹介してもらった。佐久間とともに本庄に戻り朱美を確認してもらった。南方朱美であるといった。朱美は老人を識別できなかったものの、南方という名前、鴨田酒造の様子のいくつかには覚えがあるという。宇多川が話すたびに朱美は思い出した。佐久間老人も再訪した。朱美は先夫殺害を除きほとんどを思い出した。残酷過ぎると宇多川からは話さなかった。昭和二十一年頃、東京に戻った。
そこに元憲兵と名乗る男が宇多川の留守中にやって来た。嫌な予感がしたので引越した。またやって来たので朱美のことは知らないと応対した。都合四、五回転居して逗子に定着した。そこで海鳴りが怖いというと溜め息をついた。朱美は宇多川が話した以上のことを話す。それは非常に現実感があるので朱美に間違いないという。しかし、二ケ月前、朱美は新聞切抜きを見つけてしまった。それから生々し首の切断面の様子とかどくどくと流れ出る血液の様子とかを思い出した。本人が知り得ない様子を怖ろしいほど現実感を持って話す。それが妻の精神をさらにおかしくしたことは間違いない。ついに先夫を殺したのは自分だ。容疑者を殺したのも自分だろうといいだしたという。宇多川が説明する。
先夫が殺害さたのは昭和十九年八月三十一日から九月一日の間、朱美は八月三十一日、憲兵に勾引されて九月二日に解放されている。先夫を殺せるはずがない。しかし先日、困った事が起きた。帰ってみると家の中が荒らされていた。妻は先夫が復讐に戻ってきたという。敦子は先夫が生存していたのかときく。申義は出征する際に武運長久の手形を神社に奉納していた。それが役に立って本人の確認ができている。生存はない。それは誰か別人の嫌がらせ、元憲兵と名乗る男の登場、あるいはその男が申義と似た男を差し向けたとかということがないかと敦子がいう。妻は先夫が訪れたのは一度だけではない、その上、先夫に犯されたという。さらに朱美は訪れた先夫を殺害して首を切断し、さらに再度訪れたのも同じく殺害し首を切断したという。妻は殺害、切断を三度繰り返したという。敦子、関口が唖然とする。関口が専門医に見せることを勧める。話しはつづく。
最初に家が荒らされた時に医者に見せようと思ったが可哀そうで見せず、一週間ずっとつき添って看病した。すこしよくなったと思ったので外出して帰宅すると、殺害を発見した。ひどい錯乱状態だった。殺してしまったのでもう来ないと思って外出した。そうしたらまた殺害した。さらに殺害した。都合三回だ。最後は大変な騒ぎだった。首を切らないという約束を破って、首を切ったという。教会に連れて行ってくれといわれた。そこで普段は見たことのない庭を見た。庭中が血の海だったという。それは三日前のことだ。昨日あたりから妻は落ち着いたが今日の葬式に出たくなかった。隣りの奥さんに頼んで外出した。隣接するとはいえ、地形が変ですぐには来られないが注意すれば様子はわかる。半年ほど前に引っ越してきた。一週間前に心配して様子を見に来てくれた。敦子がいう。
お話をうかがって深刻な事態であることはわかった。しかし何か釈然としないものが残る。幻覚とだけ考えられないものもあるようだという。関口が先夫殺害事件を解決しようとしているのかと驚く。神経症の患者が見る幻覚には想像を絶するものがある。奥様の幻覚はそれで十分納得できる。それに事件は幻覚症状の引き金を引いただけだという。敦子はなおもその解決が奥様の治療に力となるとこだわる。宇多川が事件について作家的興味を持ったようだ。また事件の解決も必要だと思ったらしい。関口に友人の探偵、榎木津に頼めないかきいてきた。自分が巻き込まれる予感に怖れをなす関口にたいし敦子が自分が依頼するといった。関口が精神科の医師に連絡すると約束した。車を待つ間に関口の心には様々な思いが去来した。握手を交した後、関口は車で帰宅する宇多川を敦子とともに見送った。
(つづく、あと2回で完結する。)





コメント 0